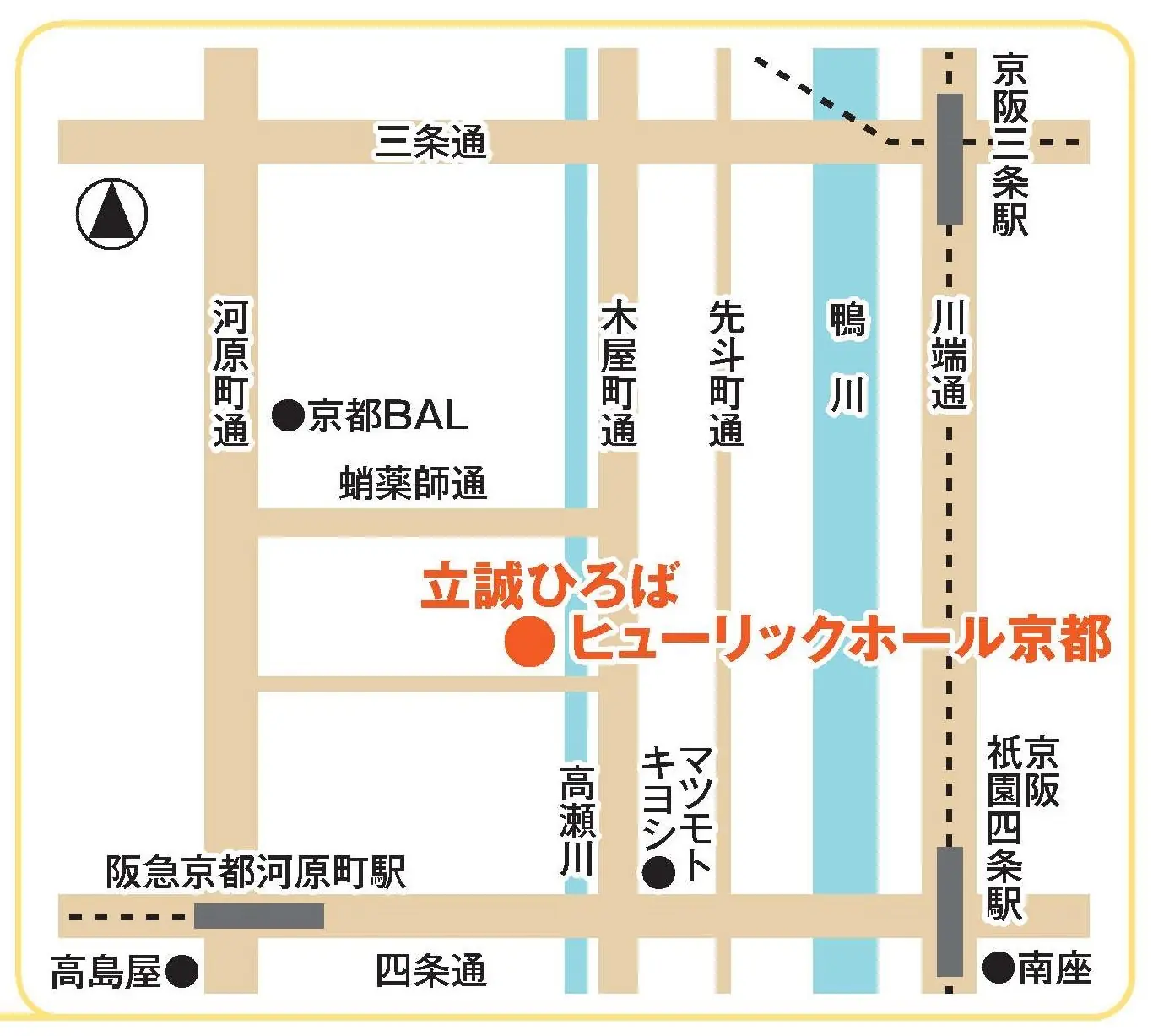この度、伏見区役所と京都工学院高等学校の協力により、未来を担う子どもたちに科学の楽しさを知ってもらうためのワークショップが開催されることとなりました
対象は、京都市内の小学4年生から中学3年生までです
保護者同伴の小学生も参加可能ですので、ぜひみなさんご参加ください!
開催概要
今回のワークショップでは、京都工学院高等学校サイエンスクラブの部員が講師を務め、一緒に様々な実験を行います
第一部: バスボム作りの体験
第二部: プログラミングを使ってマシーンを動かし、タイムを競う挑戦をします!
実施日時
令和7年9月27日(土曜日)の午後1時30分から午後4時まで(午後1時から受付開始)
会場
伏見区役所2階 講堂(伏見区鷹匠町39-2)
対象
伏見区内に在住または通学している小学4年生から中学3年生(小学生は保護者同伴必須)
定員
20名(多数抽選
当選者のみ連絡します)
参加費
無料
募集期間
令和7年8月6日(水曜日)から令和7年9月16日(火曜日)まで
申込方法
以下の内容を記入し、伏見区役所ホームページの入力フォームから申し込んでください:
- 応募者の氏名(ふりがな)
- 日中連絡可能な電話番号
- 住所
- メールアドレス
- 通学中の学校名・学年
補足: 定員20名(多数抽選で当選者のみ連絡します)
インターネット環境がない方は、担当課までご連絡ください
担当課
京都市伏見区役所地域力推進室企画担当
電話:075-611-1295
掲載確認日:2025年08月01日
前の記事: « 京都市、TikTokと連携して京まふを盛り上げる取り組みを発表
次の記事: 京都市が避難所運営マニュアルの改定に向け市民参加を募集 »
新着記事