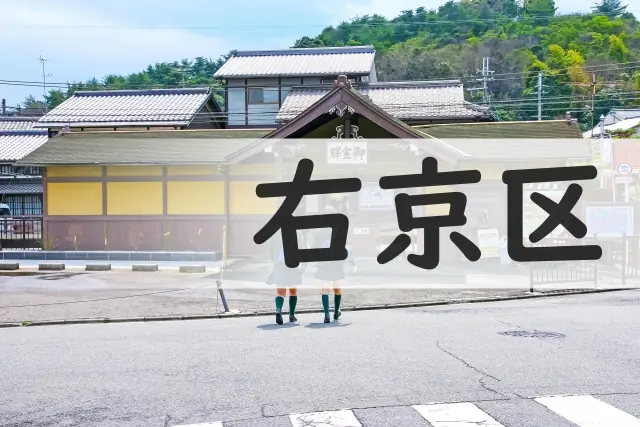ふるさと納税で昨年度(2024年度)の寄付がまとまり、京都市が全国の自治体で12番目に多い115億円の寄付を集めました
これは、京都市が地域を盛り上げるためにとても大切なニュースです!
総務省によると、昨年度に全国の自治体に寄付された金額は約1兆2728億円で、前年より1553億円も増加しました
実はこれで、5年連続で過去最高を更新しているんです
都道府県別では、京都府全体で228億円が集まり、前年に比べて31億円、つまり15%も増加しました
この寄付金、何かの役に立つと思うと嬉しいですよね
その中でも、特に寄付が多かったのが京都市で、前年より15%ほど増加して115億円
全国でも12番目に多く、これは誇らしいですよね!
この増加の理由は、京都市が返礼品の数を大幅に増やしたからです
例えば、旅行クーポンや洋菓子が特に人気で、多くの人がそれを目当てに寄付をしているんです
京都府内では、寄付金が多い自治体は他にもあり、亀岡市が43億8234万円、京丹後市が23億753万円、京都府が5億6210万円、福知山市が5億1787万円と続きます
さまざまな地域が頑張っていますね!
ただ、ふるさと納税を使って他の自治体に寄付をすると、今住んでいる自治体に納めるべき税金が減ることになります
今年度(2025年度)、京都市では約91億円の住民税が減少する見通しです
これはちょっと心配なニュースでもありますが、地域活性化のためには大切な一歩だと思います
旅行クーポンとは、特定の旅行商品やサービスに利用できる割引券のことで、寄付者が京都市に納税した際に受け取ります。特に観光が盛んな京都市では、旅行クーポンが地元の観光業にとても役立っています。観光名所がたくさんある京都ならではの特典と言えますね。これを使って旅行に行くと、経済にも良い影響を与えてくれるので、ぜひ皆さんも利用してみてはいかがでしょうか!
- ふるさと納税とは、自分の住んでいる地域以外の自治体に寄付ができる制度で、その寄付金に対してお礼ともらえる返礼品が魅力的です。
- 返礼品とは、寄付をしてくれた人に感謝の気持ちを込めて自治体が送る品物のこと。地元の特産品などが多いです。
- 地域活性化とは、特定の地域を元気にするために、産業を盛り上げたり、観光を促進したりすることを指します。
前の記事: « 京都府南部に竜巻注意情報が発表!気象現象の理解と対策
次の記事: 防災システム会社アークシステムが京都で脱税問題に直面 »
新着記事