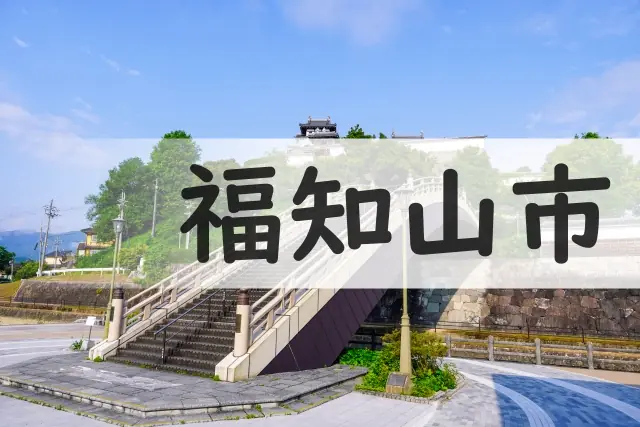
今年の節分、2月2日に福知山市の大原神社では、ちょっと変わった豆まきの行事が行われました
この日は、集まった皆さんが通常の「鬼は外、福は内」というかけ声の代わりに、なんと「鬼は内、福は外」と声を上げながら豆をまくのです
このユニークな風習は、鬼が改心して福の神になるという願いを込めたものです
大原神社では、多くの地元の住民や神社関係者が参加し、盛り上がりを見せました
まず宮司が桃の木でできた弓を使って、境内の四方に矢を放ちます
矢を放った後は、「鬼は内、福は外」という声と共に豆をまき、同時に爆竹の音が響き渡ると、鬼が現れました
参拝者は、元気なかけ声をあげながら豆をまき、鬼は本殿に入っていきます
しばらくしてから鬼は「福の神」になって再登場し、本殿からは「福豆」がまかれました
この福豆をつかもうと、参拝者たちは両手を高くあげ、夢中でつかみ取ろうとしていました
参加者の中には「今年1年、健康で平和に過ごせることを願います」と話していた方もいて、地元の皆さんがこの伝統行事に込めた想いが伝わってきました
私たちもこのような行事を通じて、地域の伝統と絆を大切にしたいですね
ピックアップ解説
「福豆」とは、節分の時期にまかれる特別なお豆です。昔から病気を追い払う力があると信じられています。京都では、この福豆をつかんだ人は、幸福が訪れると言われています。福豆をつかむために、参加者が元気に豆をまく様子はとても楽しげです。地域の伝統行事である福豆まきが、京都の文化をさらに魅力的にしています。
キーワード解説
- 「鬼は内、福は外」とは、福知山市の大原神社で行われる豆まきの特別なかけ声です。鬼が改心して福の神になるように願う意味が込められています。
- 福豆は、節分にまかれる豆のことで、幸運を呼び込むとされています。豆をまいて鬼を追い払い、福を呼び込む伝統が根付いています。
- 節分は、立春の前日を指し、冬から春への移り変わりを祝う行事です。豆まきを通じて、悪い影を追い払い、幸せを呼び込むと信じられています。
前の記事: « 京都に襲いかかる寒気と大雪についての最新情報
次の記事: 京丹波町で行われた獅子と狛犬の講演会の様子 »
新着記事


