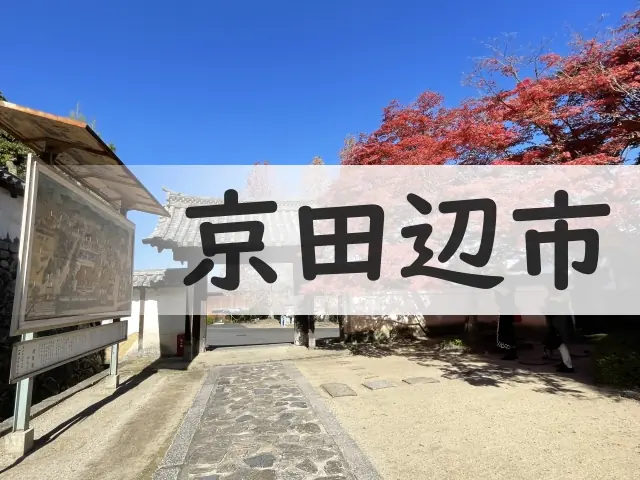
京田辺市の一休寺で行われている「一休寺納豆」の仕込み作業が注目を集めています
この納豆は、なんと室町時代から続いている伝統的な食品なんです
一休さんが製法を伝えたとされ、その独特の味わいは一度食べてみる価値があるんですよ
一休寺納豆の特徴は、粘り気が少なく、塩辛い味わいです
これは、蒸した大豆に「はったい粉」と「麹菌」を混ぜて発酵させた後、木桶に移し、塩や水を加えながら天日干しを続けて作られます
なかなか面白い製造工程ですね!
今年は大豆が不作でしたが、田邊宗一住職は、例年通り桶をかき混ぜ、水分を飛ばす作業を行っているそうです
1つの桶には約60キロの大豆が使われ、今年は4桶分が仕込まれているとのこと
これも、京都の伝統を守るための大切な作業です
この仕込みは来年の5月頃まで続けられ、その後、1年間の熟成を経て、見事な納豆が完成します
一休寺の納豆は、単なる食品ではなく、京都の文化の一部でもあるのです
ぜひ一度、味わってみてはいかがでしょうか?
ピックアップ解説
一休寺納豆は一休さんが製法を伝えたとされる伝統的な納豆です。京都の中でも有名なこの納豆は、粘り気が少なく、塩辛い独特な風味があります。室町時代から続くレシピは、今でも大切に守られ、地元の人々に愛されています。また、発酵には麹菌を使っていますが、これはご飯を発酵させて美味しいお酒を作るためにも必要な菌です。納豆ができるまでには、何ヶ月も時間がかかりますが、その手間暇が美味しさを生んでいるのです。
前の記事: « 伏見区にあるエミ・クラフトの不正請求問題の経過と影響
次の記事: 猛暑続く京都市で最高気温38.7度、厳重警戒を »
新着記事


