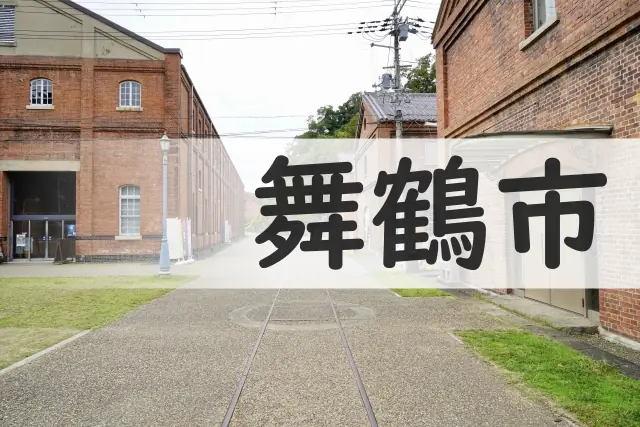
舞鶴市にある浜の赤れんが博物館で、鉄道とれんがに関する興味深い講演が行われました
この講演は、同館の顧問である水野信太郎・北翔大名誉教授が担当し、れんががいかにして鉄道施設に多く使われてきたかについてお話しされました
水野教授は「れんが産業にとって、鉄道が最大の消費先だった」と言い、その理由としてれんがの特徴である『腐らず、燃えず、長持ちする』ことを挙げました
れんがが使用される鉄道施設には、トンネルや橋、さらにはプラットフォームなど様々なものがあり、実際に現役で使われているものも多く存在しています
例えば、JR新橋と有楽町を結ぶ高架橋もその一つです
水野教授は関東の駅で見つけた古いれんが造りのプラットフォームについてのエピソードを語り、「何の修理もせずほったらかしでもしっかり残っている
このれんがの丈夫さが改めて確認できた」とその強度を称賛しました
れんがは文明の発展とともに、私たちの生活を支えてきた建材なのです
今回の講演は、連続講座「日本の近代化とれんが」の一環として行われており、次回は11月1日の午後2時から「灯台とれんが」をテーマに予定されています
京都や舞鶴の文化に深く関係する内容が多く、地域の魅力を再発見する絶好の機会です
皆さんもぜひ参加してみてください
れんがとは、古代ローマの時代から使われている建材の一つで、粘土を焼いて作られます。日本でも多くの歴史的建造物に使われてきており、その耐久性が評価されてきました。特に、舞鶴市の赤れんがは、明治時代に建てられたものが多く、地域の特徴を形作っています。また、れんがの赤い色合いは、見る人に温かみを与えるため、今でも人気のある素材です。
- れんがとは、粘土を高温で焼き固めた建材のことです。耐久性があり、古くから様々な建物に使われています。
- 鉄道とは、鉄のレールの上を走る電車や列車のことです。人や物を運ぶために重要な交通手段です。
- 近代化とは、社会や経済、技術などが進化し、今の生活に近づいていくことを指します。交通や建築に大きな影響を及ぼします。
前の記事: « 京都大学と共同で進化する人工知能ロボット技術
次の記事: 南区で高級腕時計詐欺事件、総額は驚きの4億2900万円 »
新着記事


