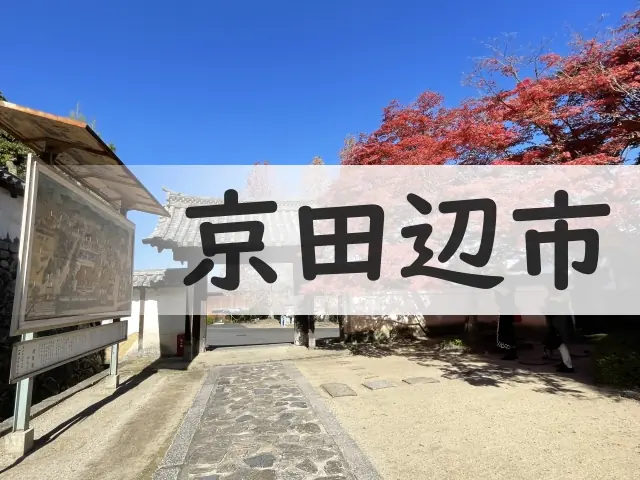
最近、京田辺市の普賢寺小学校で、絵本を通じて「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」について考える講演会が開催されました
保護者や地域の方々、約20名が参加し、自分たちの身近にある偏見について熱心に話し合いました
この講演は、京田辺市立中央図書館の元館長で、35年間も司書を勤めた釘本容子さん(61)が担当
その知識と経験を元に、参加者が気軽に話せる雰囲気を作り出しました
会場には、テーマに合わせた約100冊の本が並べられ、多くの絵本が紹介されました
釘本さんはまず、「せかいでさいしょにズボンをはいた女の子」や「ぼくのスカート」といった、ジェンダーに関する偏見を考える絵本を読み聞かせてくれました
これらの絵本は、子どもでも分かりやすく、親子で一緒に楽しむことができます
講演後のディスカッションでは、参加者が自分の経験をシェアしました
例えば、「子どもがピンクを好きだったのに、『男の子だから青がいいよ』と無意識に色を勧めてしまった」といった声もあり、自身の行動を振り返るきっかけとなったようです
子どもが同小学校に通う松本絢子さん(44)はこう話します
「人権やジェンダーといった難しいテーマも、絵本を通すことで分かりやすくなると思います
ぜひ子どもと一緒に読みたいですね」
このような取り組みが増えることで、京田辺市全体がもっと豊かに、そして優しい社会になれたら素晴らしいですね
「アンコンシャスバイアス」とは、無意識に持つ偏見のことです。私たちは知らず知らずのうちに、他人を見たり判断する際に、人種や性別、年齢などに基づいて判断することがあります。京田辺市の講演会では、絵本を通じてこの偏見を考えることが目的だったので、子どもたちも理解しやすく、自分の行動を見つめ直す良い機会になりました。こうした教育的な活動は、地域全体の意識を変えていく可能性があります。
- アンコンシャスバイアスとは、無意識のうちに持っている偏見のことを指します。例えば、ある人を見るとき、その人の外見によって判断を下すことがあります。これは誰にでもある自然な反応ですが、気づかないうちに他の人を傷つけることにもなりかねません。
- 絵本とは、子ども向けの本の一種で、絵と文字が組み合わさったものです。物語を通じて子どもたちが想像力や思いやりを育む手助けをします。絵本には教育的な要素も多く、楽しいだけでなく学びも得ることができます。
- ジェンダーとは、社会的に構築された性別のことを指します。性別は生物学的なものだけでなく、文化や社会によっても影響を受けるため、男女が持つ役割や期待が異なることがあります。ジェンダーに対する理解を深めることが、現代社会では特に重要です。
前の記事: « 大山崎町の老人福祉センターで行われた教養講座の魅力とは?
次の記事: 左京区で楽しむ岡崎さくら回廊十石舟の春の風物詩 »
新着記事


