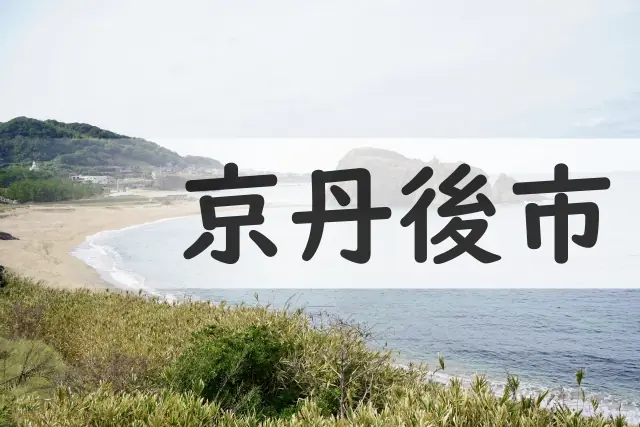
京都府の京丹後市にある弥栄町の黒部地区では、地域の住民たちが協力して深田部神社の秋の祭礼に欠かせない踊り子のためのわらじや草履を作り上げました
この伝統行事は冬の恒例となっており、有志たちは「踊り子の小中学生が気持ちよく履いてくれることを願っている」と語っています
この祭りは毎年10月の上旬に行われ、厄年の男性が演じる鬼役の「猿田彦(さるたひこ)」が神社一帯を歩き回ります
そして、頭にシャグマと呼ばれる飾りをつけた小中学生18人が太鼓を奏でながら、約5キロの距離を練り歩きます
実は、この踊り子たちが履くわらじや草履は、昔は踊り子の祖父母たちが昭和30年代ごろまで作っていました
しかし、時が経つにつれて家庭で調達するのが難しくなり、地域の老人会がその役割を引き継いできました
しかし、高齢化や人口減少が進み、老人会の活動も難しくなり、約10年前から地域の役員たちが地元の高齢者から技術を学び、作り方を手順書にまとめてきたのです
現在は、住民有志がその伝統を受け継いでいます
最近では、60〜70代の住民5人が昨年末から2月中旬にかけて公民館に集まり、宵宮を含む行事用のわらじ36足、祭り本番用の草履36足、そして鬼役のための草履1足の合計73足を手作業で編み上げました
作業では、わらを木づちで柔らかくほぐし、鼻緒には布を巻いて子どもたちが痛い思いをしないように配慮しています
有志の代表、小谷昇さん(74)とメンバーの吉岡千代子さん(73)は「子どもたちの晴れ舞台を支え続けられるよう、技術を伝承していきたい」と力強く語りました
地域の伝統を守るための10年の努力が、今後も続くことを願っています
「わらじ」とは、主に草やわらで作られる履物の一種です。昔は日本の各地でよく見られ、農作業を行う際に使われていました。特に、京都のような伝統文化が色濃く残る地域では、祭りや行事に欠かせない存在でもあります。わらじの良いところは、足にフィットすることと、通気性が良いことです。今はなかなか見かけることが少なくなりましたが、見た目や履き心地を楽しむために、再び注目されることを期待したいですね。
前の記事: « 綾部市で味わう春の花々と楽しいイベント情報
次の記事: 福知山市児童科学館で蝶とトンボの展示開催! »
新着記事


