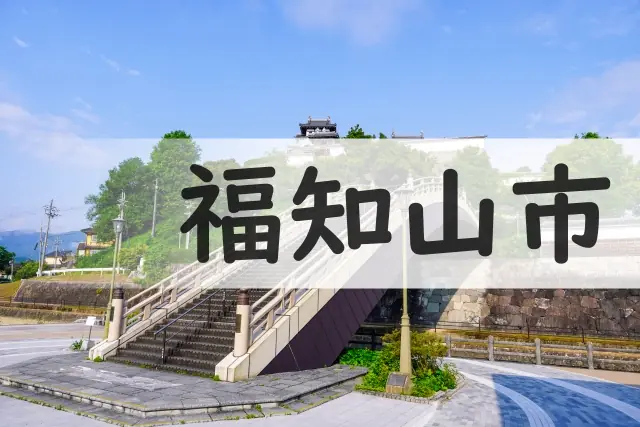
福知山市では、昭和初期までに一般の家庭で使われていた暖房器具を紹介する展示会が開かれています
この催しは、福知山市内にある丹波生活衣館が主催し、昔の生活の知恵を見学できる貴重な機会となっています
会場には、大正から昭和初期にかけて使用されていた居間が再現されており、当時の人々がどのように暖を取っていたのかを間近で見ることができます
展示されている「いろり」や「火鉢」は、当時の日本の家庭には欠かせないアイテムでした
また、寒さから身を守るために工夫されてきた衣類も展示されています
特に、「綿入れ」と呼ばれる保温性に優れた衣類には、生活をより快適にするための工夫が詰まっています
さらに、布団の中に入れて使う「安全ごたつ」という道具も展示されています
この道具は、ひっくり返しても中の火が落ちにくいように設計されていて、安全性が高められているそうです
展示を手がけた丹波生活衣館の山内麻美さんは、「今と比べると便利ではない時代だと思いますが、その時代の方々の知恵や工夫を見ていただけたら」と話しています
この展示会は、皆さんが失われつつある昔の暮らしの知恵を知り、京都の文化を再認識する良い機会になると思います
興味のある方は、是非訪れてみてください
展示会は来月(3月)2日まで開催されます
「いろり」とは、昔の日本で主に家の中心に作られた暖房用の囲炉裏のことで、食事の調理や家族団らんの場としても重宝されていました。いろりでは、薪を燃やし、その熱で部屋を暖めるだけでなく、炭火を使って料理をすることもできました。当時の人々にとって、いろりはただの暖房器具以上の存在でした。囲炉裏を囲んで家族が集まり、思い出話に花を咲かせたことでしょう。今では見かけることが少なくなったいろりですが、その風景には温かみがあり、京都の歴史的な家屋では今も大切にされています。
- 暖房器具とは、寒い時期に室内を温めるための機械や器具のことです。昔は薪や石炭を使った道具が一般的でしたが、現代では電気やガスを使ったものが多くなっています。
- 生活衣館とは、地域の歴史や生活文化を保存し、伝えるための施設のことです。京都には多くの風情ある生活衣館があり、観光客だけでなく地元の人々にも親しまれています。
- 安全ごたつとは、内部に火を入れて使う暖房用具で、ひっくり返しても安全に火が入ったままの構造が特徴です。昔の家庭では欠かせない存在でしたが、現代ではあまり見かけなくなっています。
前の記事: « 長岡京市の国道171号で事故、高齢男性が死亡
次の記事: 京都共栄学園の渡邊似胡選手が新記録! »
新着記事


