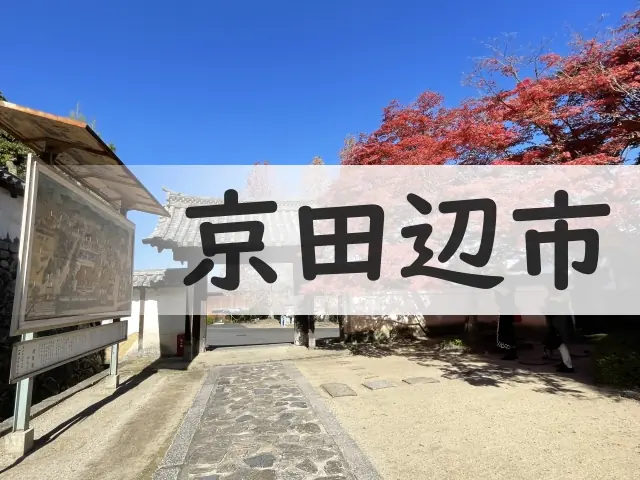
京田辺市の嬉しいニュースが飛び込んできました!無形民俗文化財である「大住隼人舞(おおすみはやとまい)」が、5月3日に大阪で開催される関西万博の関西パビリオン内で披露されることになりました
この舞いは、京都の魅力を発信するための一環として行われ、宇治田楽まつり(宇治市)なども参加します
舞を披露するのは保存会の約20人で、午前11時半から正午の間に行われます
この隼人舞は、奈良時代以前から続く伝統的な舞で、九州南部から移住した「隼人」と呼ばれる人々が伝えてきたものです
移住地である京田辺市の大住地区では、長年その継承が途絶えてしまっていましたが、1971年に鹿児島県の類似の舞を参考に復元されました
現在では、毎年、地区内の月読神社と天津神社での秋祭りに奉納されています
隼人舞は神話「海幸彦と山幸彦」を源流としており、舞う場所を清める「お祓い」や、神々を呼び招く「神招き」、悪魔を追い払う「振剣」など、6種類の舞があります
舞いにはそれぞれ異なる衣装や小物が使われるのも魅力です
また、海幸彦が海におぼれる様子を表現するための所作も含まれ、観る人を惹きつけます
今年の披露では、地元の中学生を中心に舞を演じる予定で、太鼓と龍笛(りゅうてき)による演奏とともに華やかな舞を見せてくれることでしょう
普段は6月末から練習を始めるところを、今年は早めにスタートし、日曜や祝日の夜に約2時間の練習を行っているそうです
保存会の石坂清会長は「日本国内はもちろん、海外の方々にもこの伝統的な舞を知ってもらいたい」と語り、指導を行っています
また、舞を演じる岩本真輝さん(17歳、大谷高校3年)は「万博で踊れるチャンスはなかなかないので、一生懸命頑張りたい」と意気込みを話していました
隼人舞は、奈良時代以前に都を守った隼人たちに由来があります。彼らは九州から移住してきた人々で、この技術が京都にも広がりました。大住地区では1971年に復元され、今も大切にされています。また、舞には神話に基づく物語があり、とても興味深いです。音楽に合わせた舞は、地域の大切な文化の一部です。京田辺市に住む私たちにとって、隼人舞は誇りです。
- 無形民俗文化財とは、伝承される文化や技術のことで、形のない文化財のことを指します。
- 大住神社とは、京田辺市にある神社で、隼人舞が毎年奉納される場所でもあります。
- 秋祭りとは、地域の神社で行われるお祭りで、収穫や豊作に感謝する行事として広く行われています。
前の記事: « 長岡京市で発生したトラックと軽自動車の玉突き事故
次の記事: 京都長岡京市での交通事故、7人が病院へ搬送される »
新着記事


