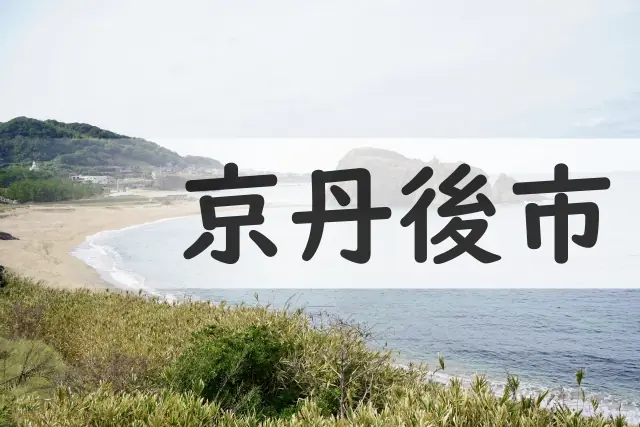
今日はちょっと特別な日です
京丹後市にある常徳寺で、98年前に起きた大地震、いわゆる丹後震災の犠牲者を供養する法要が行われました
この法要には、地元の方々が参加し、供養塔に刻まれた名前を見ながら、当時の悲惨な状況に思いをはせました
丹後震災は、1927年の3月7日、現在の京丹後市網野町で発生した、マグニチュード7.3の大地震です
多くの人が夕食の準備をしていた時に起こり、火災が発生しました
その結果、約3千人もの方が命を落としました
これは非常に大きな被害です
供養塔は、震災の翌年28年9月に建立され、碑文には地元の旧口大野村での被害状況が紹介されています
例えば、「死者五十二名、負傷者百二十九名」といった情報が刻まれています
このように、私たちが忘れてはいけない歴史があります
法要には、地元の住民や関係者が集まり、原智功住職(86)のお話を聞きました
住職は、当時において自らが住職だった祖父から聞いたことを教えてくれました
なんと、当日は寺の境内に1メートルもの雪が積もっており、お葬式が行われていたのです
その最中に地震が起き、なんと棺が一瞬、土の中から跳ね上がったと言います
参列者が本堂を見ると、崩れ落ちた屋根の下から、かろうじて山門だけが残っていたそうです
この話には、当時の恐ろしさが伝わりますね
法要の間、参加者たちは静かに手を合わせ、亡くなった方々を思い出し、また防災への誓いを新たにしました
京都の歴史を知ることは、私たちの未来を守ることにもつながります
これからも、京丹後市が安全で美しい町であるように心から願い、地域の絆を深めていきたいですね
丹後震災とは、1927年の大地震で、京丹後市周辺で発生しました。この災害は、約3千人の命を奪い、地域に大きな影響を与えました。特に、地震の後に起きた火災が多くの被害をもたらしたため、歴史を知ることが未来の防災に繋がります。私たちがこの災害を忘れず、地域を守るためにどう行動すべきか、しっかりと考えていきたいものです。
- 丹後震災とは、1927年に京丹後市で発生した地震で、約3千人が亡くなった大災害です。地震の後には火災も発生し、多くの街が壊滅しました。
- 供養塔とは、亡くなった方々を供養するために建てられた塔のことです。特に災害や戦争で亡くなった方々のために作られることが多いです。
- 防災とは、災害から身を守るための活動や対策のことを指します。実際に、災害が起こった時にどう行動すべきかを考えることが重要です。
前の記事: « 南丹市で68歳男性が74歳女性を傷害、衝撃の事件発生
次の記事: 京都府・トランプ政権の関税政策に対する具体的な対策について »
新着記事


